# 共創ワークショップ
「変化を行動へ」
生成AIや対話の力を活かし、問いをひらき、共に学び、共に未来を描く。
多様な立場をつなぐ"実践型ワークショップ"を行います。
- ① 生成AIで「問いをひらく力」を育む
- 生成AIの基本的な仕組みや特徴を学ぶだけでなく、参加者自身の業務課題にひもづけた具体的な活用事例を交えながら、"自分ごと"としてAIの活用を考えるワークショップです。
対話と内省を重ねる設計により、単なるスキル習得にとどまらず、共創型の学びと業務改善へのヒントを得られる機会を提供します。
- ② 対話と実践でつくる、オーダーメイドの学びの場
- C-tableでは、自治体・企業・教育機関など多様なパートナーと共に、目的に応じた「共創型ワークショップ」を企画・実施しています。
たとえば、市民とともにサービスを構想するシビックテックスクールや、地域の未来を担う高校生向けのデザイン思考プログラム、自治体職員向けの業務改善型DX研修など、参加者の「自分ごと化」を促しながら、対話と実践を通じた学びと変化を支援してきました。
内容やテーマはご相談に応じて柔軟に設計します。お気軽にご相談ください。
- ③ 専門ファシリテーターによる、文脈に即した研修設計
- 私たちのワークショップは、単なる知識提供ではありません。
実践経験豊富なファシリテーターが対話を重ねながら、参加者の課題や現場の状況に応じたオーダーメイドのプログラムを設計します。
現場に根ざした学びが行動変容や組織の変化に繋がるよう、問いを起点とした"意味ある学び"を支えます。
ファシリテータープロフィール
- 認定ワークショップデザイナー:本田久仁子
- 対話と問いを軸に、行政・教育・地域の現場で共創型の実践を多数デザイン。 都市と地方をつなぐプロジェクトにも多数関与。生成AIやデジタルツールの文脈にも強く、「仕組み」と「人」の両面から変化を支援します。


私たちのアプローチ


- 型だけではない、
対話から立ち上がる"実践のデザイン" - 私たちのワークショップは、単なるテンプレートの導入ではありません。
認定ワークショップデザイナーが事前に丁寧なヒアリングを行い、課題の構造や背景に応じたオーダーメイドの場を設計します。
対話から生まれる本質的な問いと、それに向き合うプロセスこそが、人と組織を前進させる力になります。生成AI活用に限らず、自治体職員研修や教育現場での共創プログラムなど、多様な現場に対応できる経験とスキルを有しています。
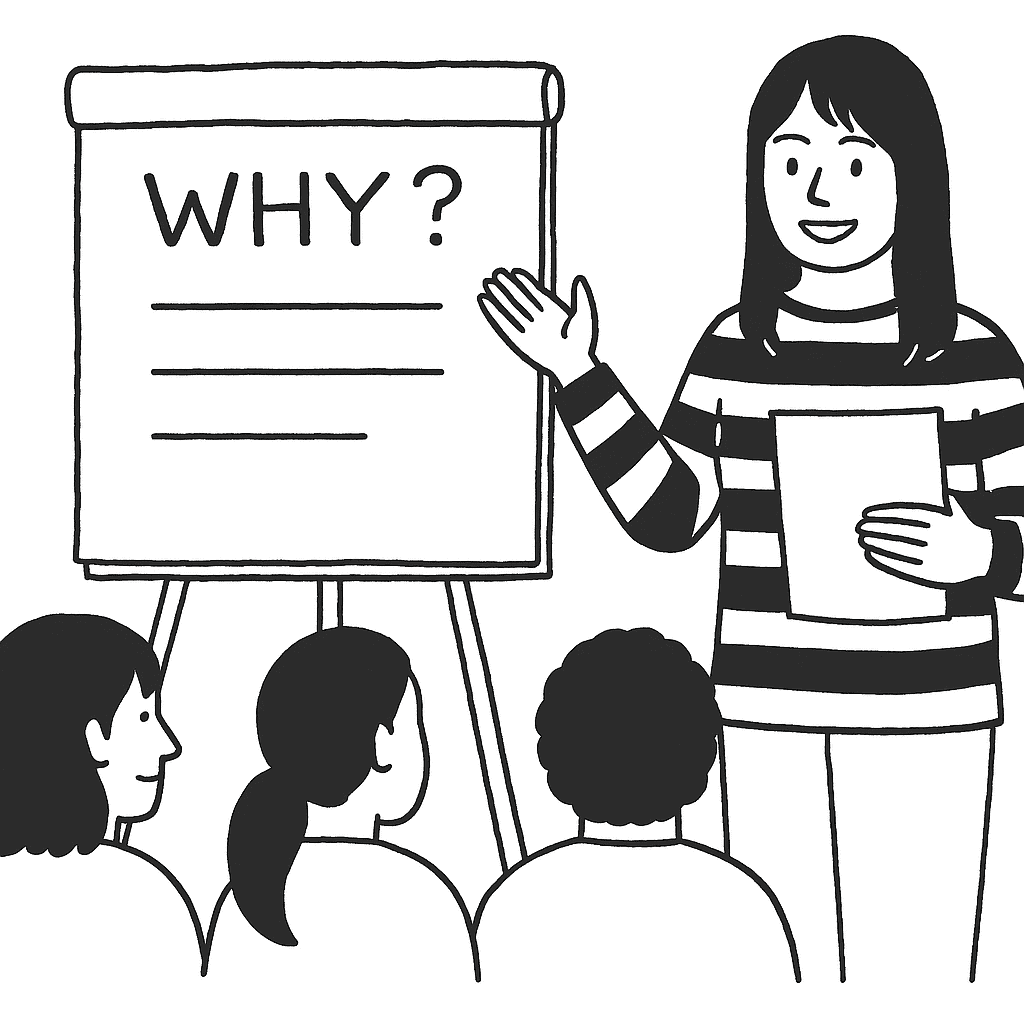
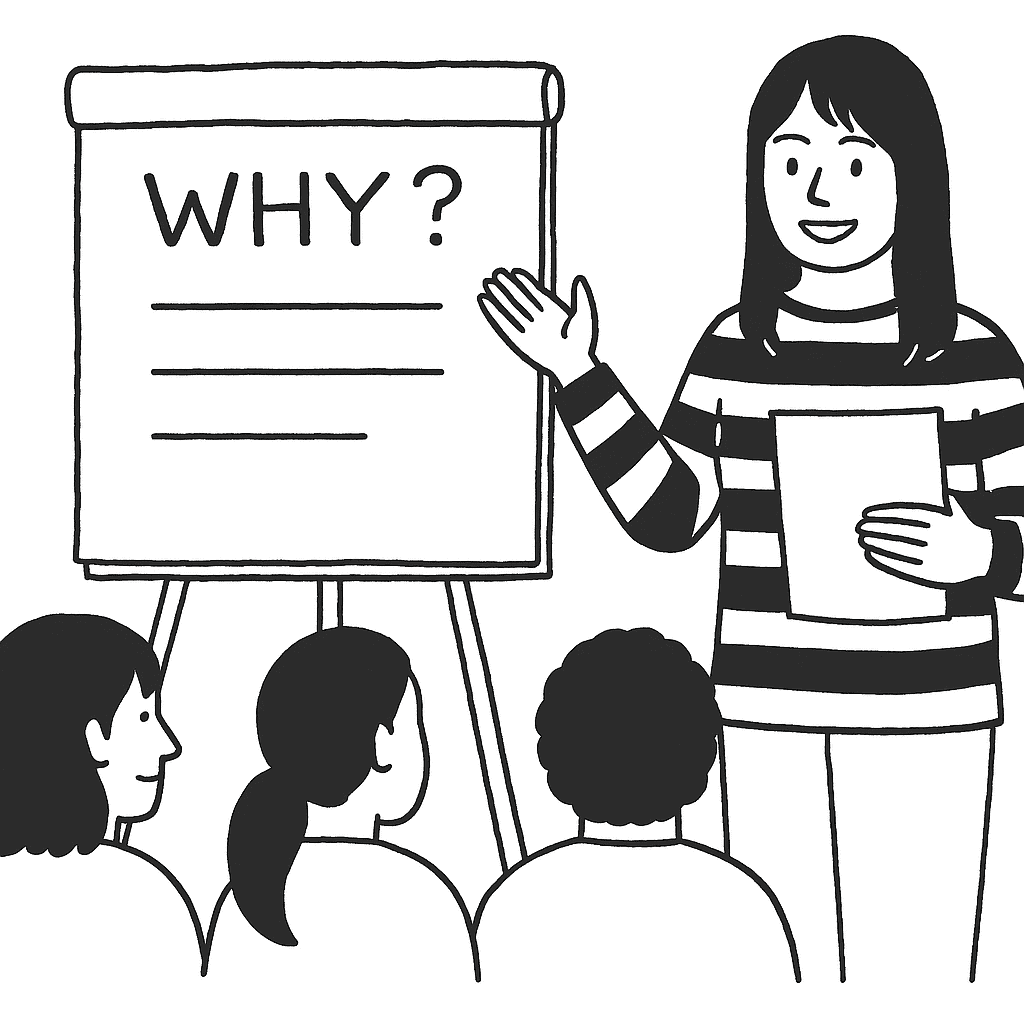
- スキルだけで終わらせない、
"意味ある学び"を支える構造 - 多くの研修やワークショップは「知って終わり」「やって終わり」になりがちです。
私たちは、「なぜやるのか」「どんな価値を生むのか」という"意味の発掘"を重視し、参加者自身の業務や現場にひもづく問いを立てるところから伴走します。
生成AIに限らず、研修をきっかけに組織文化の変容や継続的な改善につながる構造設計を行います。
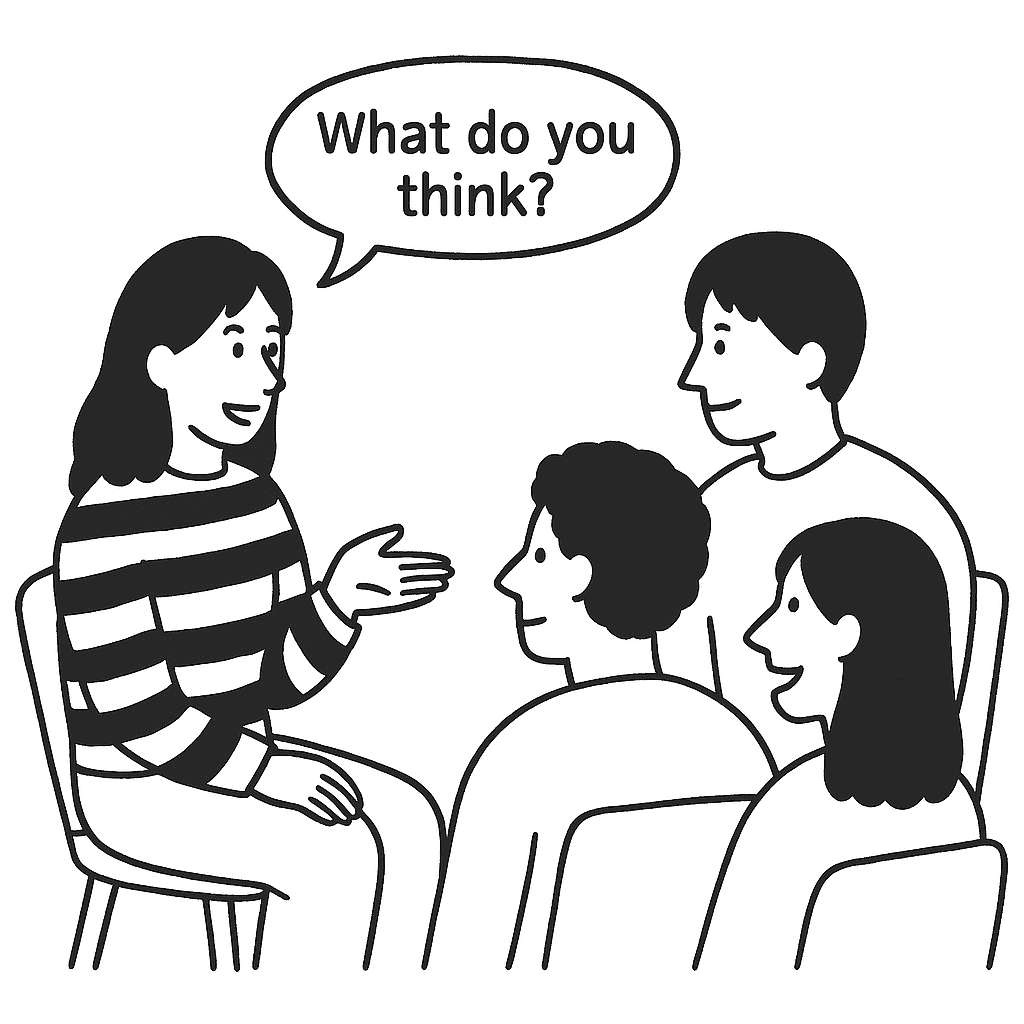
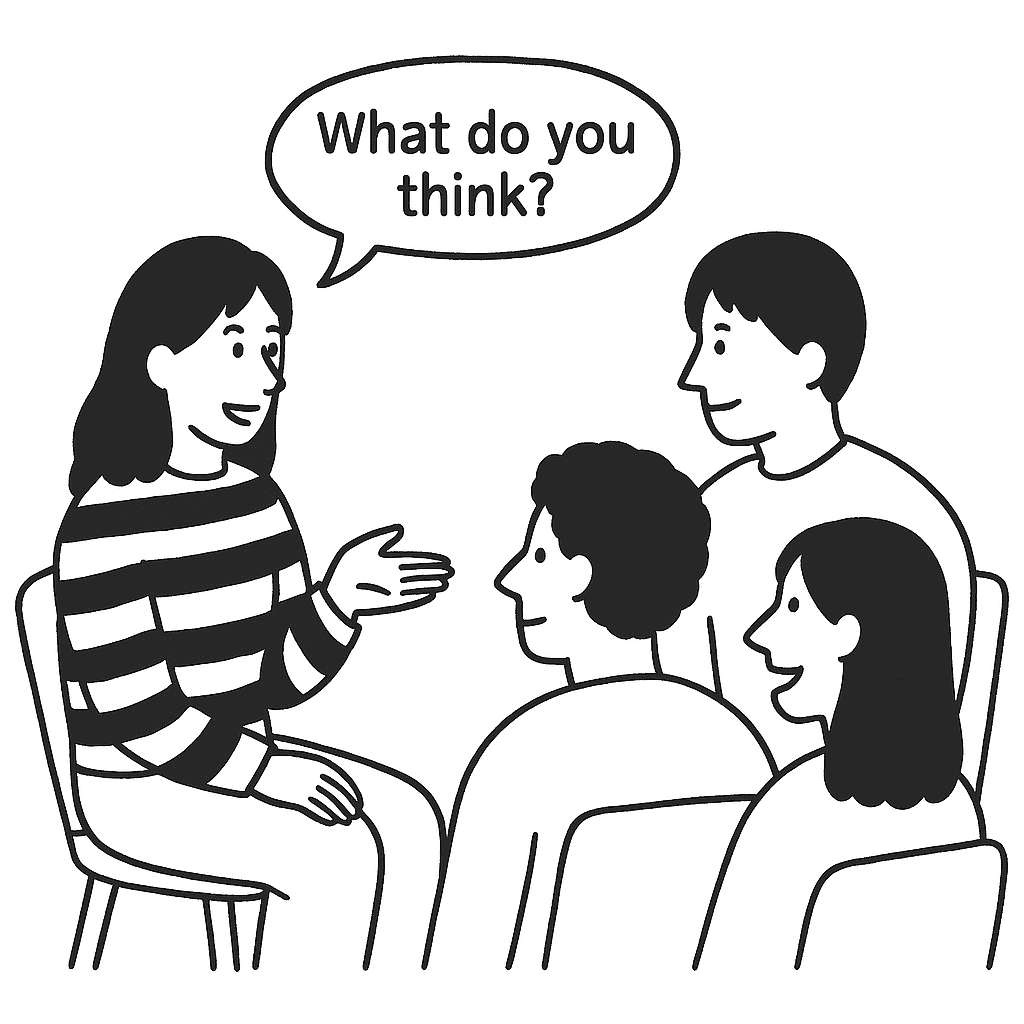
- 現場から立ち上げる、
"越境するまなび"のデザイン - 官民、都市と地方、企業と自治体、ベテランと若手。
立場や文脈の異なる現場をつなぎ、一方通行でない学びと実践の循環をつくります。
対話と共創を軸に、参加者それぞれの文脈にフィットする形で汎用的かつ実践的なスキルや視点を育むことが可能です。
地方でも都市部でも、現場の変化を促す“学びの場”として機能するようデザインします。
# まちづくりDX
「課題を機会に」
人口減少社会が抱える課題を機会と捉え、
デジタルを活用した新しいまちづくりを行います。
- ① まちに新しい仕事を創る
- 働く世代が地方に定住できない大きな理由は「仕事」です。この課題を機会と捉え、
「デジタル活用」と「都市部との連携」により、まちに新しい産業や雇用の創出を構想・実現します。
- ② 新しい公共サービスを創る
- 労働人口減少、ライフスタイルの多様化により、地方では民間・公共問わず住民向けサービスの維持・向上が難しくなっていきます。
この課題を機会と捉え、「官民連携」×「デジタル活用」でまちの人が幸せに暮らすための「新しいサービスモデル」を構想・実現します。
私たちのアプローチ
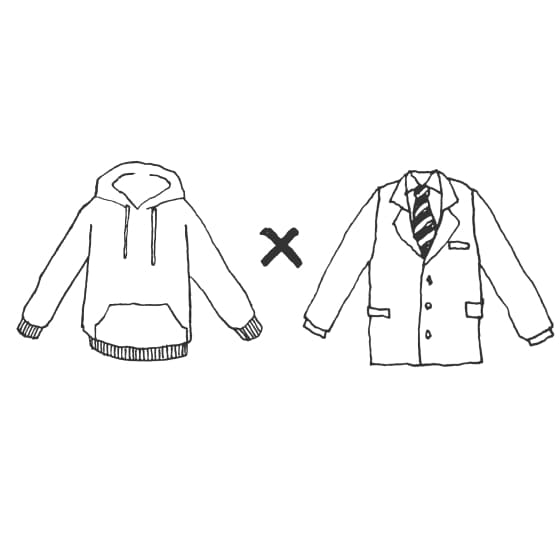
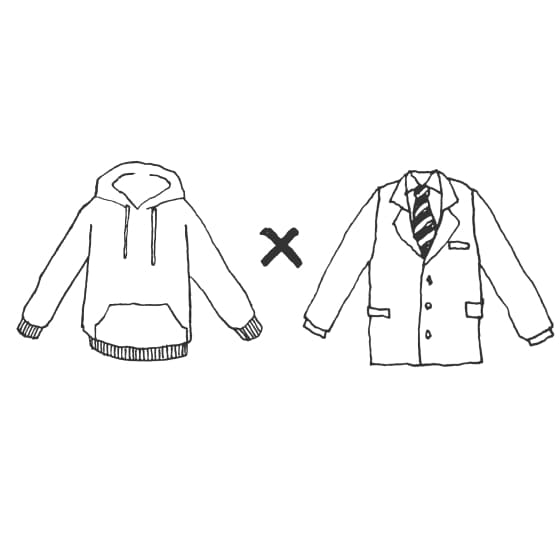
- 官だけでも民だけでもない、
官民連携のまちづくり - 政府の試算によると、日本の労働人口は2040年までに1,200万人減少することが予測されています。労働人口の減少、ライフスタイルも多様化していく中で、民間は市場が縮小し、行政は税収が減少、必要な公共サービスを提供できなくなっていきます。このような背景の中、「住民の生活に大切なサービスを官民一緒に提供すること」が未来のまちづくりの重要なテーマになっています。
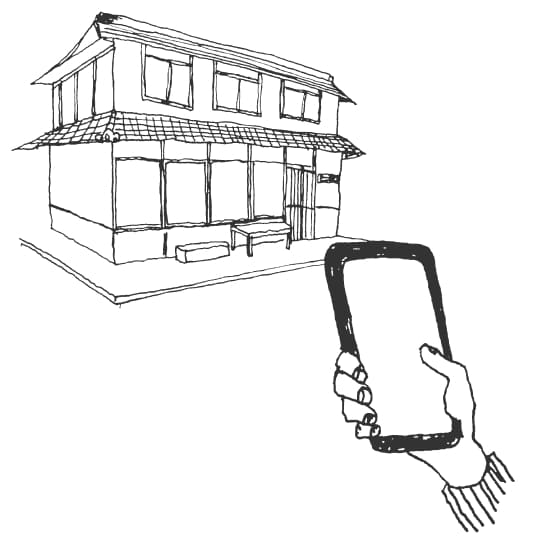
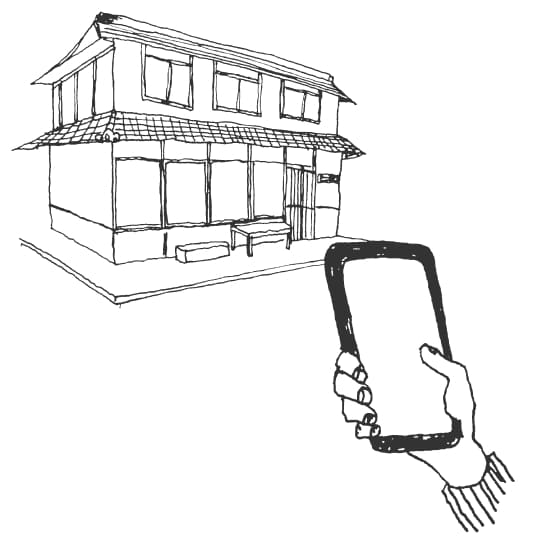
- 建物だけではない、
デジタルサービスのまちづくり - 「まちづくり」というと建物のリノベーションなどがイメージされますが、私たちが主に取り組むのはデジタルを活用した「サービス」です。デジタル化による生産性の向上、イノベーション(事業の革新)の恩恵は人口の少ない地方でこそ大きなものですが、地方でのデジタル化はなかなか進みません。それは地域の当事者にデジタルに精通した人材が不足しているからです。私たちはデジタルプロフェッショナルとして地域で活躍するデジタル人材の育成と共に生活者視点でのデジタルサービスを構想、実現します。


- 地域内だけでない、
都市部と連携したまちづくり - 労働人口減少は日本全体の課題です。都市部の民間事業者においても国内市場の縮小は避けられず、競争が激化しています。その中で、デジタル技術を活用した地方展開構想を持つ事業者も増えています。私たちは、このような都市部の事業者と地域事業者それぞれのビジネスニーズを理解し、双方にメリットのある枠組みの構想・実行をします。
# 事業DX
「違いを価値に」モノやアイディアが溢れる時代に
「好き」にカタチを与え、デジタルを活用した事業づくりを行います。
- ① 新しい事業の開発・運営
- これまでなかった事業を自社や当事者となるパートナーとの提携により、開発・運営します。
- ② 新しい事業のプロデュース、マーケティング支援
- 新しい取り組みを行う企業、団体の事業構想・ブランディング、マーケティングをアツく支援します。
私たちのアプローチ
- 誰かの欲しいものではなく、
自分の中の必然性をカタチにする - 物やアイディアが溢れ、人工知能が爆発的な進化を遂げる今、問題解決の手法はいくらでも出てくる時代になりました。一方で私たちにはそれぞれに「そもそも何が問題なのか?」を見出す力を問われています。マーケティング的な発想ではなく「自分の中の必然性」からコンセプトをカタチにし、これまでなかった価値を世界に増やすこと。それが私たちの事業開発アプローチです。
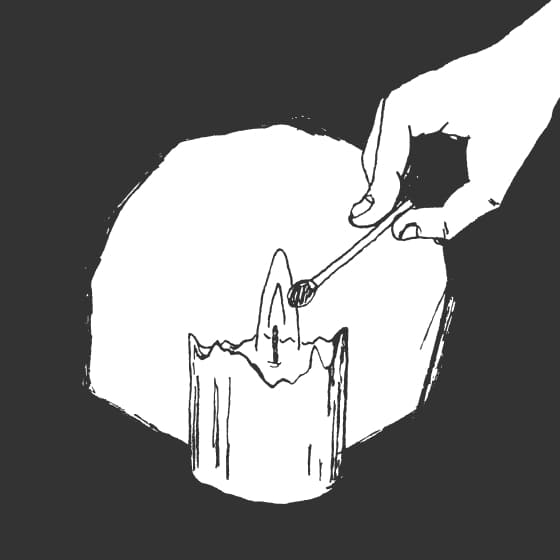
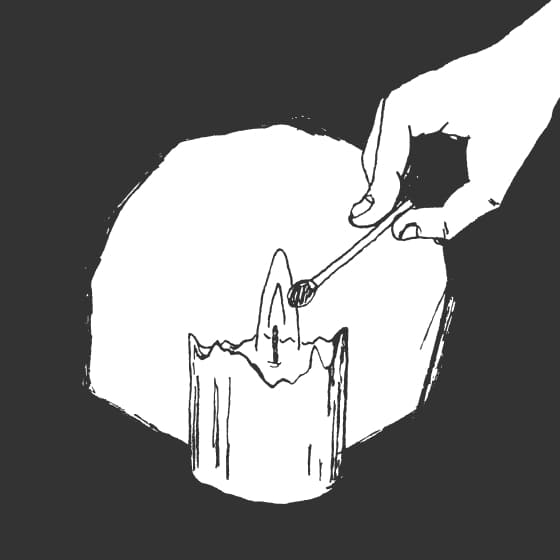
- ソリューションではなく、
新しい意味を創る - 「暗い部屋を明るくする。」かつてその役割は「ロウソク」が担っていました。しかし電球が発明され、今やほぼすべての部屋に備え付けられています。では、ロウソクのビジネスは滅びたでしょうか?
2010年、世界のロウソク消費量は30年前のおよそ3倍(EUだけで年間約70万トン)に増えています。今、人々はロウソクに明るさを求めていません。部屋でリラックスするために、むしろ部屋を「暗くする」ために使っています。ロウソクには「新しい意味」があるのです。
※参考: https://www.youtube.com/watch?v=WDn3yQKfpqY&feature=youtu.be
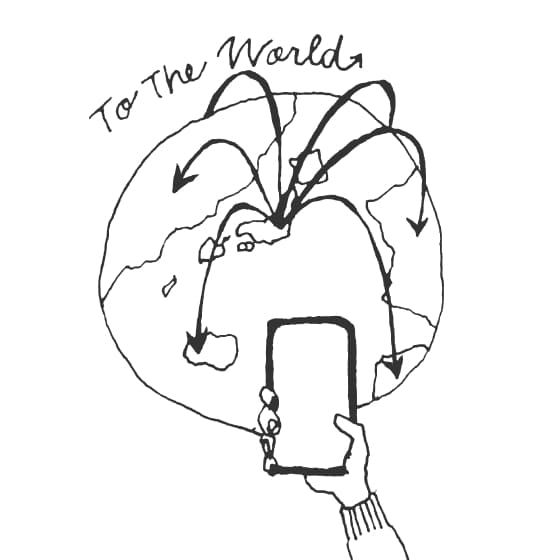
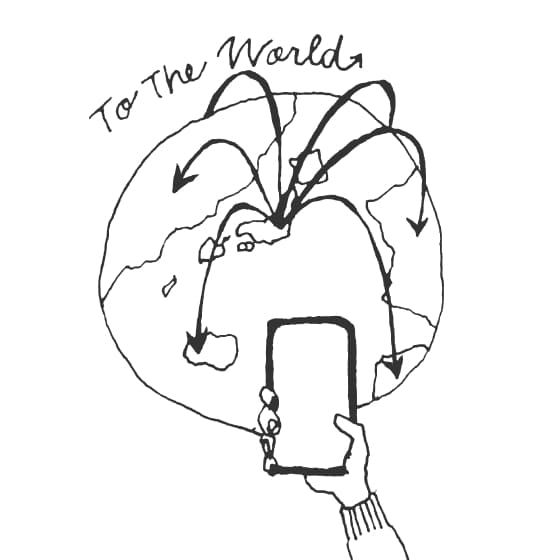
- 違いが価値となる新しいビジネスを
デジタルで世界に届ける - これまで地域のスモールビジネスは限られた商圏、限られたユーザに対してサービス提供することを目的としていました。しかしインターネットの爆発的普及は、多くの人やモノ、情報を、場所や時間の制約から解き放ちました。Facebookは世界で24.1億人、Instagramは10億人が利用しています(※)。スマートフォンで世界はつながっています。
私たちはデジタル技術を駆使し、地域にとらわれず、「違いこそが価値」となる「新しいビジネス」を構想・実行・支援します。
※参考:https://growthseed.jp/experts/sns/number-of-users/


















